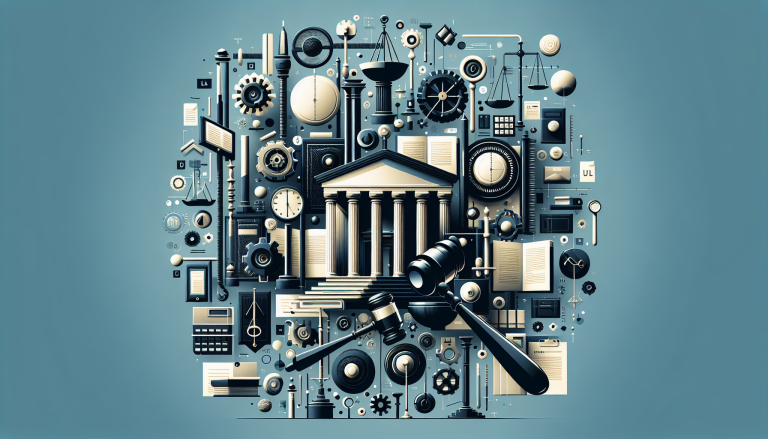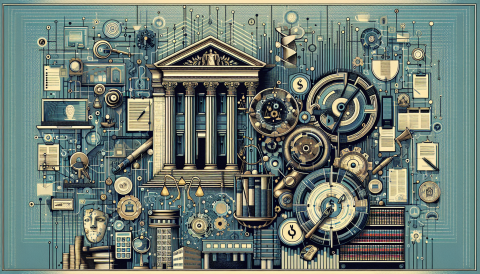はじめに
2025年4月23日、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)はQualcomm Inc. v. Apple Inc.事件において、特許無効審判(IPR)手続きにおける「出願人が認めた先行技術」(Applicant Admitted Prior Art: AAPA)の使用範囲に関する判決を下しました。この判決は、35 U.S.C. § 311(b)の解釈を明確にし、AAPAがIPR請求の「基礎」(basis)として使用できないことを明確に示しています。本判決によれば、IPR請求者が自身の請求書においてAAPAを明示的に「基礎」として記載している場合、その請求は法的要件を満たさないため却下されるべきとされました。CAFCは「in combination」ルール(AAPAが他の先行技術と組み合わせて使用される場合は許容されるという考え)を明確に否定し、IPR請求の基礎となり得るのは「特許または印刷刊行物から成る先行技術のみ」であるという法文の厳格な解釈を支持しました。
この判決は、特許権者と特許無効を求める当事者双方のIPR戦略に大きな影響を与えることになります。特許権者にとっては防御の新たな選択肢が生まれる一方、IPR請求者は請求書の作成においてAAPAの扱いに細心の注意を払う必要があります。本記事では、この重要判決の詳細と、特許実務家が今後のIPR戦略立案において考慮すべきポイントを解説します。
事件の背景と経緯
特許と訴訟の概要
本件で争われたのは、複数の電源を使用する集積回路装置に関するQualcommの米国特許第8,063,674号(以下「’674特許」)です。この特許は、集積回路装置が「パワーダウン」する際に発生する問題を解決するための技術を開示しています。
2018年、Appleは’674特許に対して2つのIPR請求を提出しました。各請求には2つの無効理由(Ground)が含まれていましたが、今回の上訴で問題となったのは「Ground 2」です。Appleは、この無効理由の「基礎」(Basis)を「出願人が認めた先行技術(AAPA)とMajcherczakの組み合わせ」(一部の請求ではMatthewsも含む)と明示的に記載していました。
本件で問題となったAAPAは、’674特許の明細書中に「PRIOR ART」と明示的にラベル付けされた図1と、それに関連する説明文(1:22-2:39)でした。具体的には、’674特許は先行技術として「パワーアップ/ダウン検出器を使用して電源オン/オフ制御(POC)信号を生成し、コアデバイスがシャットダウンされたときにI/Oデバイスに指示する」従来の解決策を記載していました。特許には、この従来技術の問題点として、「特定の状況下では検出器の三つのトランジスタがオンとなり、I/O電源から接地に大量の電流が流れ、不必要な電力を消費する」ことが記載されていました。Appleは、このAAPAとMajcherczakおよびMatthews特許を組み合わせることで、’674特許の請求項が自明であると主張したのです。
2020年1月、特許審判部(Patent Trial and Appeal Board、以下「PTAB」)はAppleのIPR請求を認め、Ground 2に基づき’674特許の請求項は無効であると判断しました。PTABは、AAPAは「特許に含まれる先行技術」であるため、§ 311(b)が定める「特許または印刷刊行物から成る先行技術」に該当すると解釈し、IPRの「基礎」として適法であると判断したのです。
Qualcommはこの決定を不服として上訴し、第一回目の上訴審(Qualcomm I)において、CAFCは2022年2月、AAPAは§ 311(b)の「特許または印刷刊行物から成る先行技術」には該当しないとの判断を示し、PTABの決定を無効としました。しかし、CAFCはAAPAが「特定の状況下では」IPRで使用できる可能性を残し、AAPAがGround 2の「基礎」となっているかどうかを再検討するよう事件をPTABに差し戻しました。
USPTOの指針とその変遷
興味深いことに、Qualcommの最初の上訴審が進行していた2020年8月、当時の米国特許商標庁(United States Patent and Trademark Office、以下「USPTO」)長官は、§ 311(b)の解釈に関する指針メモランダムを公表しました。このメモランダムでは、AAPAは§ 311(b)の「特許または印刷刊行物から成る先行技術」には該当しないとしつつも、「他の特許文書と併用する場合」にはAAPAがIPR手続きにおける自明性の判断を支持する証拠として使用できる可能性を示唆していました。
さらに、Qualcomm I判決後の2022年6月、USPTOは改訂指針を発表しました。この改訂指針では「in combination」ルール(組み合わせルール)を採用し、「IPR請求が少なくとも1つの先行技術特許または印刷刊行物と組み合わせて明細書中の自白(AAPA)に依拠する場合、それらの自白は請求の『基礎』を形成するものではなく、PTABによって特許性の分析において考慮されなければならない」としました。
この改訂指針に従い、PTABは差戻し後の審理において再びAppleの主張を認め、AAPAはGround 2の「基礎」ではないとして、’674特許の請求項は無効であるとの判断を下しました。これに対してQualcommが再度上訴し、2025年4月23日のCAFC判決(Qualcomm II)に至ったのです。
連邦巡回裁判所の法的分析
35 U.S.C. § 311(b)の法解釈
Qualcomm II判決において、CAFCは§ 311(b)の解釈に関して明確な立場を示しました。
35 U.S.C. § 311(b)は以下のように規定しています:
「IPR請求者は、第102条または第103条に基づく理由により、かつ特許または印刷刊行物から成る先行技術のみに基づいて、特許の1つまたは複数の請求項の無効を求めることができる」(”A petitioner in an IPR may request to cancel as unpatentable 1 or more claims of a patent only on a ground that could be raised under section 102 or 103 and only on the basis of prior art consisting of patents or printed publications“)(強調追加)
CAFCは、PTABとUSPTOの改訂指針が採用した「in combination」ルールは§ 311(b)の文言の素直な解釈に反すると判断しました。裁判所の見解によれば、IPR請求の「基礎」には特許または印刷刊行物から成る先行技術のみが含まれるべきであり、AAPAはその定義に該当しないため、AAPAは単独でも他の先行技術との組み合わせであっても、IPR請求の「基礎」として使用することはできないのです。
CAFCは、「『依拠』(reliance)と『基礎』(basis)を混同してはならない」と強調しました。AAPAが他の先行技術特許や印刷刊行物と組み合わせて使用されていることは、AAPAが請求の「基礎」に含まれていないことを意味するものではないとの判断を示したのです。
請求の「基礎」(basis)とAAPAの関係
CAFCは、「IPR請求者は自身の請求のマスターである」との原則を強調しました。これは、請求者が自らの請求内容を定義し、その内容に責任を持つという法的原則を意味します。つまり、請求者が請求書において特定の記載方法を選択した場合、後になってその選択を否定することはできないということです。
本件では、Appleの請求書の冒頭に掲載された表において、Ground 2の「基礎」が明確に「AAPA in view of Majcherczak」(およびMatthews)と記載されていました。CAFCは、この明示的な記載こそが決定的であり、Appleは自らの請求書の記載に拘束されるべきであると判断しました。
CAFCは「AAPAと先行技術特許または印刷刊行物との組み合わせに『依拠』していることは、AAPAが請求の『基礎』に含まれているかどうかを判断する上で決定的ではないが、Appleの請求書のような明示的な記載は決定的である」と述べ、Appleの請求書の記載からは、AAPAが確かにGround 2の「基礎」の一部となっていることが明らかであるとの判断を示しました。
判決の実務的影響
IPR戦略への影響
本判決を受けて、特許権者と特許無効を求める当事者双方がIPR戦略を見直す必要があります。
特許権者側の防御戦略としては、IPR請求者がAAPAを「基礎」として明示的に記載している場合、§ 311(b)違反を主張してIPR請求の却下を求めることができます。また、明細書中の先行技術の記述方法についても、将来的なIPR対策を念頭に置いた慎重な検討が必要になるでしょう。
一方、特許無効を求める側は、IPR請求書の作成において、AAPAを無効理由の「基礎」として明示的に記載することを避けるべきです。具体的には、IPR請求書における「基礎」の欄に特許または印刷刊行物のみを記載し、AAPAはあくまで参考情報または背景知識として言及するにとどめるべきでしょう。
また、「基礎」としてのAAPAの使用を回避するためには、AAPAに記載された技術的特徴と同等の内容を開示する特許文献や印刷刊行物を見つけ出し、それらを「基礎」として使用することも検討すべきです。
許容されるAAPAの使用法
CAFCは本判決において、AAPAをIPRの「基礎」として使用することは§ 311(b)に違反するとしつつも、「AAPAをIPRで部分的に利用できる場合がある」ことも認めています。具体的には、以下のような用途が考えられます:
当業者の一般的知識の証拠としての使用:AAPAは、当該技術分野における当業者の一般的知識レベルを示す証拠として使用可能です。
組み合わせの動機付けの補強:複数の先行技術を組み合わせる動機付けの存在を示す補助的証拠としてAAPAを利用することができます。
クレーム限定の補完:先行技術に明示的に開示されていない特徴が、当業者にとって自明であることを示す証拠としてAAPAを使用できる可能性があります。
ただし、これらの用途においても、AAPAは「基礎」ではなく補助的な役割にとどまるべきであり、IPR請求の「基礎」は依然として「特許または印刷刊行物から成る先行技術」でなければならないことに注意が必要です。
今後の展望
残された疑問点
本判決は§ 311(b)の解釈を明確にしましたが、いくつかの疑問点も残されています。
まず、「基礎」の定義に関して、CAFCは明示的に「基礎」と記載されている場合は明確だとしましたが、そのような明示的な記載がない場合に何が「基礎」を構成するのかについては、さらなる判例の蓄積が必要です。
また、PTABは今後、本判決に従ってAAPAの使用を制限する方向で実務を変更するでしょうが、どのような場合にAAPAが「基礎」ではなく補助的な証拠として認められるのかについての基準は、さらなる明確化が必要です。
さらに、本判決を受けて特許出願人は、明細書中での先行技術の記述方法を見直す可能性があります。先行技術として明示的に認めることの戦略的意義と、将来のIPR対策のバランスをどう取るべきかは、特許実務家にとって重要な検討課題となるでしょう。
結論
Qualcomm Inc. v. Apple Inc.事件におけるCAFC判決は、IPR手続きにおけるAAPAの使用に関する重要な指針を示しました。AAPAはIPR請求の「基礎」として使用することはできないものの、当業者の一般的知識の証拠や、組み合わせの動機付けを示す補助的証拠としての役割は認められる可能性があります。
特許実務家は、この判決を踏まえて、IPR請求書の作成方法や特許明細書における先行技術の記述方法を見直す必要があるでしょう。明示的にAAPAを「基礎」と記載することを避け、必要に応じて同等の内容を開示する特許または印刷刊行物を見つけ出すことが重要です。
また、この判決は「IPR請求者は自身の請求のマスターである」という原則を再確認しました。IPR請求者は自らの記載に拘束されるため、請求書の記載には細心の注意を払うべきです。適切なIPR戦略の立案には、§ 311(b)の制限を十分に理解し、AAPAの適切な利用法を見極めることが不可欠となるでしょう。