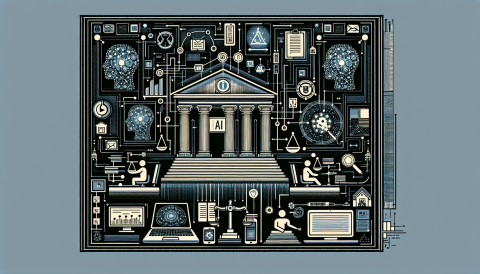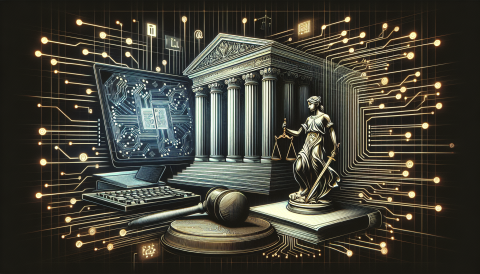2025年3月18日、コロンビア特別区巡回控訴裁判所(United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit、以下「D.C.巡回控訴裁判所」)はThaler v. Perlmutter事件において、人工知能(AI)単独で作成された作品は著作権保護の対象外であるという判断を下しました。この判決は「人間の著作者性」を著作権保護の基本原則として確立し、AIの急速な進化に直面する知的財産法制度の重要な指針を示しました。
事件の概要とその背景
AIと知的財産の関係が議論される中、Thaler v. Perlmutter事件は著作権法におけるAIの位置づけを明確にする重要な判例となりました。本件は、知的財産権の保護対象を「人間の創造性」に限定するという法的伝統と、急速に進化するAI技術がもたらす新たな創作形態との緊張関係を浮き彫りにしています。
事件の事実関係
Stephen Thaler博士は、コンピュータサイエンティストとして「Creativity Machine」と名付けた生成AIシステムを開発しました。このシステムは、ニューラルネットワーク技術を応用し、既存の情報を分析・再構成して新たな創作物を生成する能力を持っています。Thaler博士はこのAIが自律的に生成した「A Recent Entrance to Paradise」という視覚的作品について著作権登録を申請しました。

この申請において、Thaler博士は下記の特徴的な主張を行いました:
- 著作権登録申請書に「著作者」としてAI自体(「Creativity Machine」)を明示的に指定
- 「著作権者」(Copyright Claimant)として自分自身を記載
- 「Author Created」の欄に「2-D artwork, Created autonomously by machine」と明記
- 著作権の移転方法として「ownership of the machine」と記載
特筆すべきは、Thaler博士自身が申請過程において伝統的な人間の著作者性を欠いておりAIによって自律的に生成されたと明確に認めたことで、この自認が後の審査過程での重要な判断材料となりました。
法的審理の経過
Thaler博士の申請は以下の経過をたどりました:
著作権局での審査(2019年):
- 登録申請の拒否(「人間の著作者要件」を根拠)
- Thaler博士による再考請求
- 著作権局登録部門による再拒否
- 著作権局審査委員会による最終拒否(「人間の創造的関与なしに作成された作品」は登録不可)
裁判所での審理(2022-2025年):
- コロンビア特別区連邦地方裁判所での提訴
- 地裁判決(Howell判事)は著作権局の決定を支持:「人間の著作者性は著作権の基盤的要件」
- D.C.巡回控訴裁判所への上訴
- 2025年3月18日、全会一致での判決(Millett巡回裁判官執筆)
特に重要な点として、地裁段階でThaler博士は「AIの創作者として自身が著作者である」という主張を新たに展開しようとしましたが、著作権局での審査段階では明示的にAIを唯一の著作者として主張していたため、この新たな主張は「権利放棄された」と判断されました。控訴審も同様に、この主張を検討対象外としています。
判決の核心:法的分析と解釈
D.C.巡回控訴裁判所のMillett裁判官が執筆した判決は、著作権法の文言解釈、立法史、過去の判例、政策的考慮に基づく詳細な分析を行い、著作者は必然的に人間でなければならないと結論づけました。
著作権法における「著作者」の解釈
判決は、1976年著作権法が「著作者」(author)を明示的に定義していないことを認めつつも、法律の体系的解釈から人間性が前提とされていると分析しました。裁判所が特に重視した条文解釈のポイントは以下の通りです:
所有権の帰属(17 U.S.C. § 201(a)):
- 著作権は最初に著作物の著作者に帰属するという規定
- 機械は法的に財産を所有できないため、著作者になれない
著作権の存続期間(17 U.S.C. § 302(a)):
- 保護期間は著作者の生存期間および死後70年間
- 機械には生命がなく、その操作可能期間は人間の寿命とは異なる単位で測られる
相続規定(17 U.S.C. § 203):
- 著作者の配偶者、子、孫への権利継承を規定
- 機械には生存配偶者も相続人もいない
著作権譲渡の要件(17 U.S.C. § 204):
- 譲渡には書面および署名が必要
- 機械は署名をする法的能力を持たない
未公表作品の保護(17 U.S.C. § 104):
- 著作者の国籍、住所に関わらず保護
- 機械にはこれらの概念が適用できない
共同著作物の定義(17 U.S.C. § 101):
- 著作者の意図による寄与の合体を要求
- 著作者には意図があるが、機械には心がなく、何も意図しない
機械への言及の文脈(著作権法全体):
- 法律内で「機械」という用語が出てくる場合、常に「著作者の道具」として扱われている
- コンピュータプログラムの定義において「機械」「装置」「処理」は同義語とされている
裁判所はこれらの条文解釈から、著作権法は著作者が人間でなければ意味をなさないと結論づけ、人間性を著作者性の必要条件と判断しました。この判断は、著作権局が1973年以来その実務規範(Compendium)において一貫して示してきた「人間の著作者要件」とも整合しています。
「職務著作」の概念と限界
Thaler博士の重要な主張の一つは、「職務著作(work for hire)」の概念を拡張解釈し、AIを「従業員」とみなすことで、その創作物に対する著作権を取得できるというものでした。判決はこの主張を以下の理由で明確に棄却しています:
条文の精密な分析(17 U.S.C. § 201(b)):
- 「雇用者…は著作者とみなされる(considered the author)」という表現が使用されている
- 「みなされる」という語は決定的役割を果たし、法的擬制を示す
- 条文は非人間の主体を直接著作者と呼ぶことを慎重に避けている
職務著作の理論的基礎:
- 職務著作は著作権帰属の瞬時の移転を規定するもので、著作者性自体の変更ではない
- 法的擬制を通じて雇用者を著作者とみなすのであり、実際に著作者にするわけではない
前提条件の欠如:
- 職務著作が適用されるためには、まず著作物が「著作者」によって作成されている必要がある
- AIが著作者になれないなら、AIの生成物に職務著作の概念を適用する余地はない
特に判決は「著作者」の定義と「職務著作」の規定を切り離して考えることはできないとし、著作物を創作した人間が存在しなければ、著作権法は適用されないと明確に述べています。
判決の理論的根拠と政策的考慮
判決では、単なる条文解釈にとどまらず、著作権法の理論的基礎と政策的考慮にも踏み込んだ分析がなされています。
著作権の存在意義と公益性
裁判所は著作権の本質的な目的について、以下の点を強調しています:
インセンティブ理論:
- 著作権法はオリジナル作品の創作を奨励するために、著者に短期間の独占を与える制度
- Google LLC v. Oracle America, Inc.判決(2021年)を参照し、著作権は著者への特別な報酬ではなく、公衆が容易に複製できる作品の創作を奨励するためのものと指摘
公益の優先:
- 最高裁は長年、著作権法は公衆の利益のためのものであり、著者のためのものではないという立場を維持
- 著作権者への報酬は二次的考慮事項であり、独占権付与の第一の目的は、著者の労働から公衆が得る一般的利益にある
機械へのインセンティブの不要性:
- 機械は経済的インセンティブに応じない
- 生き物ではなく、報酬を求めず、経済的誘因に反応しない
これらの分析から、裁判所は著作権保護の目的が「人間の創造性」を奨励することにあり、機械に著作権を与えることは著作権法の目的達成に寄与しないと結論づけています。
憲法上の論点と限定的判断
判決は、著作権局が主張した「憲法自体が人間の著作者性を要求している」という議論については、判断を回避しています:
- 法令解釈により著作権法が人間の著作者性を要求していると判断されたため、憲法上の問題には踏み込まない
- 憲法の「著作者」(Authors)の解釈は、今回の判決では必要ない
この判断は、連邦裁判所の伝統的な「憲法判断回避の原則」に沿ったものであり、必要以上に広範な憲法解釈を避ける司法的抑制を示しています。
判決の実務的影響
本判決は、AI技術と著作権法の交差点において、重要な境界線を設定しました。しかし同時に、AIと人間の協働による創作という現実的な問題については、明確な解決策を提供していません。
AI支援による創作物の著作権保護
判決では、AIが「単独の著作者」として認められないことを明確にする一方で、AIを創作ツールとして使用した人間の著作権については判断を回避しています:
- 特定の作品にAIがどの程度寄与したかという線引きの議論は本件では関係ない
- それは、Thaler博士が本件において対象となる作品の唯一の著作者としてCreativity Machineを挙げ、それが機械であり人間ではないからである
この点について、判決は以下の重要な指摘をしています:
- 人間の著作者性の要件は、AIを利用して作成された作品の保護を妨げるものではない
- 重要なのは、AIが創作した作品の著作者が、人間であるかAI自体であるかという点である
これにより、AI支援による創作物の著作権保護可能性は残されていますが、どの程度の人間の関与が必要かという重要な問いは今後の課題として残されました。
特許弁理士にとっての実務的留意点
本判決を踏まえた実務的アプローチとして、特に以下の点が重要です:
創作過程の詳細な文書化:
- AIツールの使用状況を記録するだけでなく、人間の創造的判断の証拠を残す
- 特に重要なのは「創作的選択」の明示:どの出力を選び、なぜ選んだか
- 修正、編集、構成の決定など、人間特有の創造的貢献を記録
AIプロンプトと人間の創造的貢献の関係:
- Allen v. Perlmutter事件の実例が示すように、複雑なプロンプト作成だけでは不十分
- 著作権局はAIツールが分析・解釈・応答する方法に対する制御の欠如を問題視
- プロンプト設計だけでなく、出力結果への人間の判断と変更が重要
クライアントへの具体的助言:
- AI生成物への依存度が高いビジネスモデルの法的リスクを明確に説明
- 「人間の創造的貢献」を最大化・文書化するプロセスの設計を推奨
- 著作権以外の保護手段(契約、営業秘密等)の検討も含めた総合的戦略
関連する判例・裁定との比較分析
Thaler v. Perlmutter判決は、知的財産法体系における「人間中心主義」の確立という点で、他の重要判例と連続性を持っています。
特許分野における類似判断
本判決と特許法における同様の論点を扱った判例には重要な並行関係があります:
Thaler v. Vidal事件(連邦巡回控訴裁判所、2022年):
- 同じThaler博士が「DABUS」というAIシステムを「発明者」として特許出願
- CAFCは「特許法における発明者は自然人でなければならない」と判示
- 最高裁は上告を棄却(2023年)し、この判断が確定
共通する法的理由づけ:
- 両判決とも法律の文言解釈を重視
- 知的財産権が「人間の創造性」を保護するという基本原則を確認
- AIを「道具」と位置づけ、「創作者/発明者」とは区別
この2つの判決は、米国知的財産法制度における「人間中心主義」の原則を、著作権と特許権という2つの主要な分野で統一的に確立しました。
著作権局のその他の判断事例
著作権局はAIと著作権の問題について、他にも注目すべき判断を下しています:
「Zarya of the Dawn」事件(2022年):
- テキストは人間が作成し、イラストはMidjourneyで生成した小説
- 著作権局は「テキスト部分のみ」に著作権登録を認め、AI生成画像には拒否
- 人間の著作者性は著作権の基本要件と改めて確認
「Théâtre D’opéra Spatial」事件(Allen v. Perlmutter):
- 600以上の詳細なプロンプトをMidjourneyに入力して生成した画像
- 著作権局は2023年に登録を拒否、現在コロラド州で訴訟継続中
- プロンプト入力は著作権で保護される表現を生み出すのに十分な創造的コントロールを示さないと判断
これらの事例は、「人間の著作者性」の範囲と限界を探る重要な参照点となっており、今後のAI支援創作に関する法的境界線の形成に影響を与えるでしょう。
まとめ:特許弁理士にとっての実務的示唆
Thaler v. Perlmutter判決は、AIのみで作成された作品は著作権法の保護対象外であるという原則を確立し、知的財産法制度における「人間の著作者性」の重要性を再確認しました。この判決は著作権の本質を「人間の創造性」を奨励することにあると位置づけ、「職務著作」などの法的擬制をAIに適用することはできないと明示しています。特許分野における類似判断とも整合し、米国知的財産法における「人間中心主義」を強化する一方、人間とAIの協働による創作物については判断を回避しており、実務家にとっては創作プロセスにおける人間の創造的関与を最大化し詳細に文書化することが不可欠となります。AI技術が進化する中でも法律の基本原則は当面維持されますが、今後も法的境界線の明確化が続くことが予想されます。