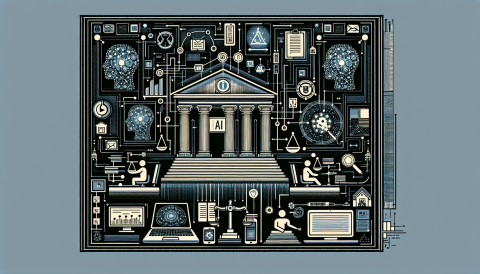最高裁判所は、アンディ・ウォーホル財団 v. ゴールドスミス事件において、ウォーホルがプリンスの著作権保護された写真を使用した場合の目的と性格がフェアユースには該当しないと判断しました。判決は、単に新たな表現やメッセージを追加するだけではフェアユースを支持しないことを明確にしました。最高裁は、オリジナルの作品と二次利用が同じ目的であり、二次利用が商業的な場合、フェアユースとみなされるためには説得力のある正当化が必要と強調しました。この判決は、フェアユースの要素を適用する方法や、著作権で保護されたさまざまな創作物に対する取り扱いについて多くの疑問を投げかけています。
ーーー
最高裁判決:Andy Warhol Foundation for the Visual Arts v. Goldsmith
5月18日、米国連邦最高裁判所は、注目されていたAndy Warhol Foundation for the Visual Arts v. Goldsmithに対して判決を下し、Andy Warhol Foundationがプリンス(Prince)として知られるアーティストの著作権で保護された写真を使用する目的および性格がフェアユース(fair use)に該当しないという見解を示しました。
特に、新しいメッセージや表現が、それだけで「使用の目的と性格」(“purpose and character of the use”) という要素をフェアユースに有利にはたらかせることができるのか、という点について、裁判所は「ノー」と回答しました。この意見はまたこの要素をどのように適用するかについて新たな問題を提起しています。この問題は、ビジュアルアートのほか、ソフトウェア、文学、音楽、映画、その他著作権によって保護されているすべての作品に影響を及ぼします。
写真をベースにしたアートは元の写真の著作権を侵害するものなのか?
1981年、Lynn Goldsmith(ゴールドスミス)は、ミュージシャンのプリンスを撮影した一連の写真を撮影しました。ゴールドスミスは、そのうちの1枚(モノクロのポートレート)をヴァニティ・フェア(Vanity Fair)誌に提供し、同誌の次号に掲載されるイラストの「アーティスト・リファレンス」として使用することを許可しました。その後、同誌はポップアーティストのアンディ・ウォーホル(Andy Warhol)に依頼し、この写真をもとにシルクスクリーンで肖像画を制作、Vanity Fair誌はプリンスに関する記事とともに掲載しました。それとは別に、ウォーホルはオレンジ色のシルクスクリーンプリントを含む13枚のシルクスクリーンプリントと、2枚の鉛筆画を制作しました。
2016年にプリンスが亡くなった後、アンディ・ウォーホル財団はコンデナストに、プリンスを記念する雑誌の号でオレンジ色のシルクスクリーン版画を使用するライセンスを提供しました。オレンジ色のプリントを見たゴールドスミスは、そのプリントが白黒写真の著作権を侵害していると考え、財団に通知しました。財団はゴールドスミスに対して宣言的判決(declaratory judgment )を求め、財団がゴールドスミスの著作権を侵害していないとの判決を求めるか、あるいは別の方法で、オレンジ色のプリントは著作権法のフェアユースの抗弁により保護されているとの判決を求める訴訟を提起しました。連邦地裁では、財団はフェアユースの主張で勝訴しましたが、第2巡回区では、財団はフェアユースを立証できなかったと判断し、逆転判決が出ていました。
フェアユースに関する4つの要素
著作権法は、著作物の使用がフェアユースに該当するかどうかを判断する際に、次の4つの要素を考慮するよう裁判所に求めています。(1)使用の目的と性質(the purpose and character of the use)、(2)著作物の性質(the nature of the copyrighted work)、(3)著作物全体に対する使用部分の量と実質性(the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole)、(4)著作物の潜在市場または価値に対する使用の影響(the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work)。17 USC. § 107. 今回の最高裁判決は、最初の要素である使用の目的と性格に関わるものです。
多数意見: 表現ではなく、使用を比較する
長年の最高裁判例は、「使用の目的と性質」の要素は、「複写者の使用が、『新たな表現、意味またはメッセージで』著作物を変更する、さらなる目的または異なる性質を持つ、新しい何かを追加するかどうか」(“whether the copier’s use ‘adds something new, with a further purpose or different character, altering’ the copyrighted work ‘with new expression, meaning or message.’”)によって評価されます。Google LLC v. Oracle Am., Inc., 141 S. Ct. 1183, 1203 (2021) (quoted Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 US 569, 578 (1994)).
この点において、今回の判決は、重要な明確化を加えました。
目的と性格に関する調査は、問題となる使用がオリジナルと異なる目的や性格を持つかどうかだけでなく、どの程度かまで問うものであるとしました。裁判所は、「何らかの新しい表現、意味、メッセージ」が追加されただけでは、フェアユースに傾くには不十分であるとしたのです。もしそれが十分であれば、著作権者の二次的著作物を創作する排他的権利を危うくすることになるからです。つまり、問題は程度の問題である、ということです。したがって、原作と二次的著作物が同じ目的を持ち、二次的利用が商業的である場合、フェアユースを正当化するためには、何らかの他の「説得力のある正当化」が必要となります。
これらの原則を適用して、最高裁は、第一の要素がフェアユースの認定を難しくしていると判断しました。決定的なのは、同裁判所が、アンディ・ウォーホルのオレンジ色のシルクスクリーン印刷物をコンデナスト社に商業的にライセンスしたことに分析を限定したことです。同裁判所は、Warholが写真に基づいてシルクスクリーン版画を作成することがフェアユースであるかどうかについては裁定を下していません。つまり、プリンスに関する記事の挿絵として雑誌で使用するために、画像を商業的にライセンスしたことに注目したのです。同裁判所は、ウォーホルがゴールドスミスの写真をコピーしたことについて、「特に説得力のある正当な理由」を見出すことができなかったとも発言しています。この結論に基づき、最高裁は第2巡回区の意見に同意し、第一の要素がフェアユースに不利な要素であるという見解を示しました。
次に、最高裁は、アンディ・ウォーホルのシルクスクリーンによるレンダリングが写真に新たな意味とメッセージを加えたため、使用の目的と性格が変容的(transformative)であるという財団の主張を退けました。その際、裁判所は、被告となった侵害者は著作物をどのように使用したかを客観的に調査しなければならず、使用者の主観的な意図や、美術評論家や裁判官が作品から識別しうる意味を調査してはならない、としました。そのアプローチを適用して、裁判所は、重要なのは、問題となった特定の使用、すなわち、プリンスに関する雑誌の記事にプリンスの肖像画を添えたイラストの文脈であることが重要であると判断しました。
賛成意見* (concurring opinion)
ゴーサッチ判事は、ジャクソン判事とともに、「財団のプリンスの画像がゴールドスミスの著作権を侵害しているかどうか」を決定するものではないことを確認し、第1の要素の焦点は、問題となった特定の作品の使用にあるべきことを強調しています。
*賛成意見とは、1人または複数の裁判官による控訴審の意見で、多数意見に記載されていない理由で、ある事件で得られた結果を支持するものです。
反対意見(dissenting opinion)
ケイガン判事は、ロバーツ最高裁判事とともに表現において重要なのは 「目的と性格」だという反対意見を述べ、多数意見が「第1要素の審理を混乱させた」と主張しました。反対意見は、多数意見に引用されているCampbell v. Acuff-Rose Music, Inc.が「新しい表現、意味、メッセージ」に明確に着目しているにもかかわらず、表現が無意味になるような基準を多数派が採用しているのを批判した内容になっています。また、今回の判決は、Google対Oracleを含むフェアユースに関する「判例に忠実でない」と指摘しました。
他者の著作物の二次的な使用はより注意するべき
裁判所は、アンディ・ウォーホルがプリンスのオレンジ色のシルクスクリーン画を制作したことではなく、コンデナスト社に対する財団のライセンスに焦点を当てることで、ウォーホルのアートワークがゴールドスミスの写真をどの程度変形しているかという難しい(transformativeに関する)問題を回避しました。また、芸術家や美術評論家の目を通して見た新しい意味やメッセージは、「使用の目的および性質」の要素を公正使用に有利にはたらかせるには不十分であるとし、明確な判断を示しました。
しかし、この判決は、裁判所がフェアユースを分析する方法をさらに複雑にする可能性のある、少なくともいくつかの疑問を提示しています。
第一に、裁判所は、オリジナルの使用と二次的な使用が密接に類似した目的と性質を共有する場合、「説得力のある正当化」(“compelling justification”)を要求するという新しい基準を確立したように思われますが、そのような「説得力のある正当化」が何であるかを明確にすることはありませんでした。裁判所は、被告人である侵害者の主観的な意図は決定打にならず、裁判所は「使用の目的と性格の客観的な指標」(“objective indicia of the use’s purpose and character,”)を考慮すべきであると述べてはいますが、それ以上の指針はほとんど示していません。何が特定の正当性を「説得力ある」ものにするのかについての意見の相違は、長引く訴訟につながる可能性があります。
第二に、裁判所は、裁判所が用途を見極めるべき一般性のレベルを明確に示していません。裁判所は、両者の用途を「プリンスに関する雑誌の記事でプリンスを描写するために使用されるプリンスの肖像画」に集約しています。しかし、すべての使用事例がそれほど明確なものであるとは限りません。多数意見は、裁判所は用途間の「差異の程度」を考慮すべきであると述べていますが、その差異をどのように測定するかについて、訴訟当事者にほとんど手段を残されていません。
最後に、この事件で最も興味深い問題である、アート作品を創作する際に、アーティストが既存の作品からどの程度の自由度を得て利用することができるのか、という点について、今回の判決では明確な回答は得られず、おそらく未解決のままです。
参考記事:Supreme Court Clarifies Copyright Fair Use Defense in Andy Warhol Foundation v. Goldsmith