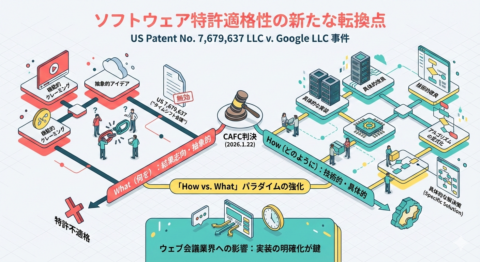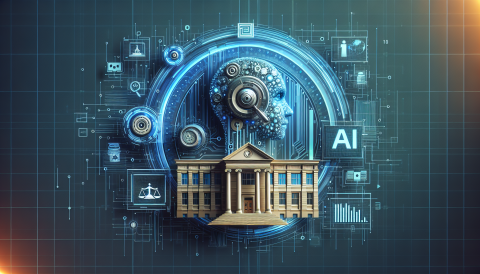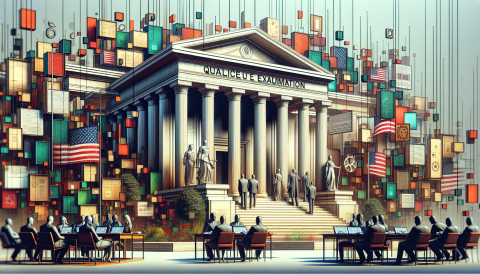古い判決ですがPTABで有益な判決として扱われているので知っておくべきです。特に構成要素の組み合わせで特許を狙う場合、どのような組み合わせなら新規性を示せるかを知る目安にもなるので、化学系やバイオ系の権利化を業務にしている人は必見です。
Ex parte Smithは、BPAI(Board of Patent Appeals and Interferences)の2012年の判決であり、PTAB(Patent Trial and Appeal Board)の有益な判決( informative decisions)の中に記載されています。この事件は、PTABが 新規性(Anticipation – 35 U.S.C.§102)について有益であるとも指摘しています。
PTABの標準業務手順( Standard Operating Procedure)によると、「有益な判決は、正当な理由がない限り、ほとんどの場合に従うべき審査会の規範を定めたものであるが、有益な判決は審査会を拘束する権限(binding authority)を持たない」とされています。
Ex parte Smithでは、BPAI(PTABの前身)は、先行技術文献の成分リストの開示が、そのリストから特定の成分のみを引用する組成物クレームを予想(anticipate)するのに十分であるかどうかを検討しました。
問題となった独立請求項1と従属請求項4は以下の通りです:
1. An aqueous hydraulic fluid composition comprising:
a first lubricant comprising at least one phospholipid; and
a second lubricant comprising an alkoxylate salt;
wherein the hydraulic fluid composition is substantially free of an oil selected from the group consisting of mineral oils, synthetic hydrocarbon oils, and mixtures thereof.
4. The aqueous hydraulic fluid composition of claim 1 wherein the alkoxylate salt comprises a calcium, magnesium or zinc salt of an alkoxylate selected from the group consisting of laurates, palmitates, oleates and stearates.
先行技術文献には、リン脂質(phospholipid )とアルコキシレート塩(alkoxylate salt)とを含む水性作動油組成物(aqueous hydraulic fluid composition)が開示されていて、その点では審判では問題になりませんでした。
組成物が実質的に油を含まないという請求項1の要件に関して、審査官は、組成物が油および/または(and/or)アルコールを含むという先行技術文献の開示に依拠しました。BPAIは、この開示が、油のみの存在、アルコールのみの存在、および両方の存在の3つの組み合わせを包含していると判断しました。BPAIは、In re Schaumann, 572 F.2d 312 (CCPA 1978) (先行技術が属(genus)を開示している場合、その属の種(species )は、種がよく定義されたまたは限定されたクラスの一部である場合には、その属の種を予想(anticipate)することができる) および In re Petering, 301 F.2d 676 (CCPA 1962) (小さな属は、属内の各種の開示であり得る) を引用して、この開示は請求項1を予想(anticipate)するのに十分であると判断しました。
これに対して、控訴人は、油分がない場合に性能が改善されたことを示す実験的証拠に頼ろうとしました。しかし、BPAIは、そのような予期せぬ結果(unexpected results)は自明性拒絶(obviousness rejection)にのみ適用でき、新規性に関わる拒絶(anticipation rejection)には使えないとしました。
請求項4で要求される特定のアルコキシレート塩(alkoxylate salt)について、BPAIは、先行技術文献には可能な添加剤の「長いリスト」が開示されていると指摘。実際には、文献には30近くの添加剤のカテゴリーが記載されており、カテゴリーごとに数個から数百個の成分が記載されていましたが、BPAIによれば、”可能性のある添加剤は無数 “でした。安定剤(Stabilizers)は添加物のカテゴリーの一つであり、許容される安定剤には「例えば、ステアリン酸マグネシウム、アルミニウムおよび/またはステアリン酸亜鉛やリシノレイン酸塩などの脂肪酸のmetal salts of fatty acids」が含まれていました。
BPAIは、請求項4の組成物に到達するためには、先行技術文献からの「成分の選択」が必要であると述べています。BPAIは、In re Arkley, 455 F.2d 586 (CCPA 1972)を引用して、新規性における拒絶が適切であるためには、先行技術文献が「クレームされた化合物を明確かつ紛れもなく(clearly and unequivocally)開示しているか、または、様々な開示を選択し、組み合わせる必要がなく(without any need for picking, choosing, and combining various disclosures)、当技術に熟練した者をその化合物に誘導しなければならない」と述べた。したがって、BPAIは、審査官は、先行技術文献が、進歩性を構成するのに十分な説明をもって請求項4に記載されている特定のアルコキシレート塩を記載していることを証明していないと結論付けました。
教訓
In re Smith事件では、3つの可能性からの選択は予期(anticipate)されましたが、数百の可能性からの選択は予期(anticipate)されませんでした。組成物は、しばしば、引用された成分の組み合わせに由来する改善された特性のために特許を取得することができます。新規性による拒絶は、改良された特性の証明では克服できないので、審査を新規性の検討から自明性の検討に移すことが重要です。先行技術の成分リストの大きさやクレームされた組成物に到達するために必要な選択の数を狭く考えすぎていることを審査官に示すために、計算や熟練した専門家からの意見表明を使用することを検討するべきでしょう。
解説
今回の判例は古いですが、PTABにおいて有益と判断されているのものなので知っておくといいでしょう。特に化学の世界では、異なる物質を混ぜた化合物をクレームすることが多いのではないでしょうか?その様な場合、この判例を知っておくと役に立つと思います。
今回の判例の重要なポイントは、先行例文献が選択肢を提示している場合、その選択肢の幅が狭ければ(判例では3つ)文献がクレームされた組み合わせを予期していると判断され、逆に文献における選択幅が無数ある場合は、特定の組み合わせは予期するものではないとするものです。
これは新規性(anticipation)に関わる問題なので、102条における拒絶に関わります。今回のEx parte Smithが適用されるかは、1つの先行例文献における選択肢の幅を見ればいいので、比較的わかりやすいと思います。
実務においてEx parte Smithが出願人に取って有利になるかは、1)先行例文献がどのような選択幅を示していて、2)クレームがどのような組み合わせをクレームしているかによって変わってきます。しかし、先行例文献における選択の余地は簡単な計算で出せることがほとんどなので、先行例文献を考慮した際の構成要素の組み合わせが明らかに多い場合は、Ex parte Smithの判例と可能な組み合わせ数を示すことで、102による拒絶を覆すことが十分可能だと思われます。
この後に予測されるのが103条における同じ先行例文献を使った自明性の拒絶ですが、103の拒絶を解消するには予期せぬ結果(unexpected results)が使えるので、クレームされている組み合わせの結果と先行例文献で語られている結果の違いに注目して差別化を図るといいでしょう。そのためにもクレームしている組み合わせの結果に関しては詳しい開示を明細書内でしておくといいですね。
TLCにおける議論
この話題は会員制コミュニティのTLCでまず最初に取り上げました。TLC内では現地プロフェッショナルのコメントなども見れてより多面的に内容が理解できます。また、TLCではOLCよりも多くの情報を取り上げています。
TLCはアメリカの知財最新情報やトレンドはもちろん、現地で日々実務に携わる弁護士やパテントエージェントの生の声が聞け、気軽にコミュニケーションが取れる今までにない新しい会員制コミュニティです。
現在第二期メンバー募集中です。詳細は以下の特設サイトに書かれているので、よかったら一度見てみて下さい。
まとめ作成者:野口剛史
元記事著者:Jacob A. Doughty. Element IP(元記事を見る)